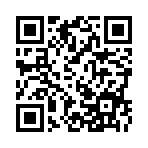› 藤本屋の和菓子彩々 › ひとり言
› 藤本屋の和菓子彩々 › ひとり言2020年09月13日
お菓子の原材料について
お菓子を買う時に選ぶ基準は、皆様どんなことでしょうか?
そんなもん、食べたいもんを買うだけやん、という声も聞こえてきそうですね。
もちろん、それでいいのです。わたしもしかり。
でも、小さなお子さんをお持ちのお父さんお母さん、また体の事に気をつかっているという方、原材料の表示をご覧になることはありませんか?
そこで、一番気になるのが添加物だと思います。
市販されている、おもに大きな工場で生産されているものの中には、流通に乗せる都合から長く日持ちをさせなければならない。
しかも柔らかい物は柔らかいままに、色も変化しないように…等様々な配慮の中、添加物に頼らざるをえないという現実があると思います。
けれど、例えばアレルギーのあるお子様などには、主となるアレルゲンの入っていないお菓子でも、なるべく添加物の入っていない物を選びたいとお考えの親御さんは多いはず。
そこで、当店では極力添加物を避け、なるべく自然のままのお菓子を召し上がっていただきたいと考えています。
あくまで材料はシンプルに、国産の物を選んでいます。
たとえば、当店の名物「茶だんご」の材料は、米粉と砂糖と抹茶と、少量の食塩。以上です。
「浜絹もち」なら砂糖と餅粉と水飴と片栗粉。
当然賞味期限が短くなるため、たくさんは買えないですよね。なので1個から買って頂いても全然かまいません。
体のことちょっと気にしているんだけどというお客様、当店に来られたらどうぞお気楽に原材料などについてお尋ねくださいね。
とはいえ、例えばコンビニのスイーツとか(和菓子も洋菓子も)、すごくおいしいですよね。私もよく買いに行っちゃいます(笑)
ホームページはこちらです。
長浜駅前通り(駅から徒歩5分) 御菓子司 藤本屋
☎ 0749(62)0804

2018年11月01日
木葉月
結びに「平成30年 木葉月」とありました。
「木葉月?」 風流な名前に魅かれます。恥ずかしながら、はじめてききました。
調べてみると「神無月」の別名、とありました。それだけしかわかりません。
木の葉の月、つまり紅葉の美しい月という意味なのでしょうか?
それとも、枯葉の舞い散る月という意味なのでしょうか?
どちらも違う??
今は紅葉といえばおおかた11月に入ってからですが、温暖化の進む前は10月にはすでに全国的に紅葉が始まっていたのかしらと、一昔前を想像したりしてみます。
そしてやがて木枯らしが吹いて赤や黄色いじゅうたんに…。きれいですね。
枯葉といえば、こんな思い出があります。
子供たちがまだほんの小さな子供だった頃のこと。近くの公園に行きました。すると、ものすごい風が吹いて、木の葉がうわ~っと一気に舞い落ちてきたのです。ざざざーっという音と共に、それはものすごい勢いで。すると、子どもが泣くんです。私にしがみついて。こわかったんでしょうね。
上を見上げてみると、木の葉がいっせいに自分を目がけて降ってくるようでした。
子どもの感受性にびっくりしました。そしてちょっぴり笑ってしまいました。

木の葉を形どったお菓子たちです。
もうじき、木の葉の季節がやってきます。
2017年12月07日
年賀状の効能
年賀状を書いている。というか、正確には印刷している。
仕事柄年末には忙しくなるので、毎年早めにこの作業に取り掛かる。
店のお得意様宛と、自分ちのと、実家の父の分と、三種類。
パソコン仕事は嫌いじゃないので、苦にはならない仕事だが、これをやっていていつも思うことがある。
「なんか味気ないなー。」と。(たぶん多くの人が思ってていることでもあると思う。)
けれど今さら手書きは無理!
だから必ず添え書きをする。
特に、日頃お世話になっている人や、懐かしい友人など。
そして毎年「去年も会えなかったねえ。残念!」と、こうなる。
高校や短大の時の友達とはもういつ以来会っていないだろう。昔の職場の同僚もそう。
でも、そう思いながら一人一人の顔を順番に思い浮かべていると、それだけでほっこりあったかい気持ちになるから不思議だ。
ついでにふっと、そういや昔あんなことあったな、こんなことあったなと、添え書きの文字の横っちょから相手との懐かしいエピソードがぽろりとこぼれ出すことがある。
(ふふふ…)
思い出に会えるのが、年賀状の効能。
さて、コーヒー片手に、今年もやりますか。どんなヒトコマにであえるやら??
2017年10月29日
毛糸の話
ある方のグログの過去記事を何気なく読んでいたら、こんな文章に出会った。
『ことしのセーター』という絵本があって、そこにとても懐かしい風景があったと。内容は…。
その日は衣替えの日で、家族がブリキの衣装ケースの中から冬物の服を取り出す。
すると、子供たちの去年のセーターはどれも小さくなっているので、お母さんやおばあちゃんが毛糸をていねいにほどいて、湯のしをして、また編みなおしてくれる…と。そんな内容だったそう。
『毛糸の湯のし』とは、火鉢に火をおこしてやかんをかけて、その蓋の穴に毛糸を通してゆっくり引いていく。これが湯のし。
お湯の蒸気で縮れた毛糸が伸びていくのだ。
このブログを読んで、思い出した。この湯のしをした毛糸を毛糸玉に丸めていくのが、子どもの仕事だったなあと。私の実家では。
私の家でもこんな風にセーターをほどいて新しい毛糸玉にしては、それが新しいセーターや手袋に変化した。
湯のしをした毛糸を『毛糸玉』にするには、二人必要だった。伸び上がった毛糸を一人が両手首に巻きつけて、もう一人が毛糸の端から引っ張って玉に巻いて行くのだ。
一人は相手が糸を引きやすいように、リズムよく右左に小刻みに手を動かす。
もう一人は玉が楕円にならないよう、均等に糸を巻きとり真ん丸い毛糸玉を作り上げる必要があった。
それがなかなかに難しい。どちらも。
私はだれと組んでいただろう? 母か姉か…。そこに父の姿は、ない。昭和だ。
しゅんしゅんと湯気のたつヤカンと、ゆるやかな毛糸のうごめきが、今も鮮明に私の記憶の中にある。もう50年近くたつというのになあ。と、知人のブログを読みながら、あったかい気持ちになった。
毛糸。ちょっと触れてみたくなる。でも、編めない。いや、編んでみようか。そんなことを思う冬の始まり。
(秋台風のうごめく中、空が冬のように鉛色なのです。まだ10月なのに気分は冬です。)

2017年10月07日
ICAN~ノーベル平和賞
核兵器廃絶運動に関わる国際NGO「ICAN」。
心から拍手を送りたいです。
そこで今日は、偶然にも夕べ読み終えた「カウントダウン・ヒロシマ」という本を紹介したいと思います。
著者は、スティーヴン・ウォーカーというロンドンの方。
この本は序盤、とてもロマンティックなエピソードから入る物語風のノンフィクションです。
あくまでも、綿密な取材を元にしたノンフィクションなのですが、その書き方からか、ぐいぐいと引き込まれていって、まるで自分がその場面場面に居合わせているような、そんな気にさせられた本です。
核兵器の開発から実験、投下、そして投下後数日までを、たくさんの人の視点を通して描かれています。読んでいるうちにそのそれぞの人物に(開発者たちにさえも)感情移入してしまっている自分に驚きました。そしてそのたびに『これはフィクションじゃないんだ。すべて本当にあったこと。歴史なんだ』と自分に言い聞かせたものです。
終盤、広島の市民たちがむごい死に方をしてゆくありさまを赤裸々に綴っています。
人間が一瞬にして炭化してしまう恐ろしい武器。人類はなんというものを作り出してしまったのかと、改めて驚愕しました。
この本は2005年に出版されていますが、どれくらいの人が読まれたでしょうか?
このノーベル平和賞をきっかけに、核兵器廃絶に向けもっと意識が高まることを願い、この本を紹介しました。
2017年08月21日
晩夏
昨日、この花が一気に花開きました。「玉すだれ」というそうです。
ずいぶん前にご近所の方から株分けしてもらったこの花、毎年どんなに枯らしても、わきから緑の新しい葉っぱがはえてきて、この時期にはきちっと花を咲かせてくれます。
本当に毎年三日と狂いなくこの時期なのです。すごいなあと感心します。
暑い暑いと言ってはいても、ちゃんと花は咲く時期を知っているし、もうじき一週間もすればコウロギが鳴き始めるだろうし、雲はごっつい入道雲から、ふわふわとした秋の雲に様変わりするし、自然界は着実に秋に向っているのですね。
そろそろ当店の和菓子も秋のものに変わります。
行く夏を惜しんで読まれた句をひとつ
「遠くにて水の輝く晩夏かな」 高柳重信
少し入り時間の早くなった夕日に輝く琵琶湖を連想します。
2017年07月05日
ネガティブ・ケイパビリティー
今日はお菓子とは全く関係のない話題ですが…。
「ネガティブ・ケイパビリティー」という言葉を聞いたことがありますか?
「答えの出ない状態に耐える力」といことだそうです。この本に教えてもらいました。
著者の帚木蓬生(ははきぎほうせい)さんという方は、小説家であり、精神科医。
この本の初めの方は、このネガティブ・ケイパビリティーの成りたちや個人に向けての効能(?)等の紹介ですが、中盤からは、今の日本の教育現場にはポジティブ・ケイパビリティ(すぐに結果に結びつけようという方向性)が主だから云々…の話があり、そして終盤になると、政治家や国家のネガティブ・ケイパビリティが足りない…という話まで。多岐にわたって興味深かったです。
中でも、この一節が印象的でした。
「平和を維持するには、偽政者は特に、そして国民ひとりひとりが、ネガティブ・ケイパビリティを発揮しなければならないのです。」
興味のある方は是非読んでみて下さい。
2017年05月23日
セイロのス
和菓子を蒸すセイロがあります。その中の底に置くス(台す? なんというんでしょう)
それをくくっている紐がゆるんだり、材料の竹の表面がささくれたりしているので、修繕しました。
まず竹を一本ずつばらします。
それをヤスリを使って表面をつるつるにし、
このような道具を使って、紐で編んでいきます。円柱状のおもりに紐を巻きつけ、あっちにやったり、こっちにやったりします。
これがおもしろいんです。
ちなみにこの道具は、先代であります義父の手作りです。赤や黒のマジックでたくさん印が書いてあります。
裏から見るとこんな感じ。
これだけの写真では出来上がる工程がわかりませんね。ごめんなさい。
でも、とりあえず出来上がりました。
たくさんあるので、一日に数枚ずつ仕上げます。
こういう手作業をしていると、心が落ち着きます。熟練してくると、木のオモリがカランコロンとリズムよく鳴って、心地よい音楽のようなんですが、私はまだまだそこまでには達しません。
このせいろで「がらたて」や「柏餅」を蒸します。大事な道具です。
☎ 0749-62-0804
ホームページはこちらです。
2017年05月20日
菓子の木型
この間テレビを見ていたら、「和菓子が消滅の危機??」なんていう文字が画面の右上にありまして、「なんのこと?」と食い入るように見ていましたらば…。
木型の職人さんがものすごく減っていて、今では数人しかいないのだとか。
とても残念なことです。
木型は和菓子職人にとって、とても大事なものです。

例えばこの木型でこんなお菓子ができます。
上生菓子「バラ」です。
それから、

この木型で、こんなお菓子ができます。
ちょっとピンボケですいません。昔よく折り菓子に入っていた上生菓子です。桜です。
これは残念ながら普段は作っておりません。
ちょっと前まで、コブログという湖北ブログをやっていまして(なくなっちゃったんですが)、その時にある方が
「ドイツのマイスター制度みたいなものが日本にもあればいいのに…。」とのコメントを寄せてくださいました。なんの話題でだったか忘れましたが、その時初めて「ドイツのマイスター制度」なるものを知りました。
で、ネットで調べてみましたら…。
〈マイスター試験に合格したマイスターたちがそれぞれの分野の後継者を育て、技術を伝承するという、ざっくり言えばドイツの職業教育法のようなもの〉、だと認識しています。
このようなものが日本にもあれば、もう少し、伝統工芸や宮大工さんや畳屋さんや鍛冶屋さんや、その他あらゆる分野の職人と言われる人々の後継者が育つかもしれないし、待遇というか、収入もよくなるかもしれないし、それがつまり、後継者不足の歯止めになるのかもしれないし、などとひとり思っておりました。
私のようなものが考えていることくらい、とおの昔に誰かがとっくに考えていらっしゃったことでもあるのでしょうがね。
和菓子職人も消えませんように!!
☎ 0749-62-0804
ホームページはこちらです。
2017年04月29日
引き札
先日、長浜城歴史博物館からこの「長浜の引き札」という冊子を頂きました。
中には、明治時代の広告であります「引き札」の写真が並んでいます。
長浜の当時の商店のものがずらり。今でも現役の商店がいくつもありました。
当店もしかり。
左下に初代與惣五郎の名前があります。実は当店は煎餅やから始まったのです。大正時代には和菓子を作る店になっていたようなのですが。引き札にはしっかり「せんべい」の文字があります。
どなたかわかりませんが、コレクターさんが残しておいて下さったこの引き札。
ページをめくっていると、明治の世に吸い込まれて行きそうな…。文明開化のにおいがいたします。
☎ 0749-62-0804
ホームページはこちらです。